春だしあったかくなったし、ランニングでも始めたいな〜という人もいるんじゃないでしょうか。かくいう自分もちょうど就職した春ころから運動不足解消のために走り始めて、かれこれ中断もありつつ細く長くランニングを続け、今はサブ3を目指しています。そんな自分の気持ちを何度となく盛り上げてくれた、走ることについて書いた本たちを紹介します。
- EAT&RUN 100マイルを走る僕の旅
- BORN TO RUN 走るために生まれた ―ウルトラランナーVS人類最強の“走る民族”
- 走ることについて語るときに僕の語ること
- 走る奴なんて馬鹿だと思ってた
- ランニングする前に読む本 最短で結果を出す科学的トレーニング
EAT&RUN 100マイルを走る僕の旅

伝説的なウルトラマラソン(160km)ランナーによる自伝的著書。これまでのレースを振り返りつつ、ビーガン(完全菜食主義者)として何を食べ、どう目標を達成してきたかについて書かれています。
著者のスコットジュレクの人生はまったく平坦ではなくて、さまざまな困難とどう向き合ってきたか、についても学ぶことが非常に多いです。彼のレース人生の中で一番ドラマティックなレースはデスバレーのバッドウォーター135マイル。コース半ばにして意識を失いそうになり、吐いて倒れて、起き上がれなくなってからの逆転劇は何度読んでも胸が熱くなります。自分にとってはランニング人生の礎のひとつとなった一冊。本当におすすめ。
BORN TO RUN 走るために生まれた ―ウルトラランナーVS人類最強の“走る民族”
“どうして動物は怪我しないのに、人間はクッション付きの靴を履いてでも怪我をするのか”という疑問を抱いた著者が、メキシコの山間部に住み、2日間素足で何百マイルも走るタラウマラ族と共に、後に伝説的に語られる山間レースを走る話。スコットジュレクもランナーとして出てきます。高野秀行氏の探検本を読んでるようで最後まで熱い気持ちで読めるし、なにより ”走るために生まれてきたのになんで走らないのか” という気持ちにさせます。
走ることについて語るときに僕の語ること
定番かもしれないのですが、やはり素晴らしい本なので紹介。”なんで走るんですか?”って聞かれると、オタク口調の早口でしか答えられないけど、格好良く答えるなら、きっと引用文の感じに近いです。
“本当に若い時期を別にすれば、人生にはどうしても優先順位というものが必要になってくる。時間とエネルギーをどのように振り分けていくかという順番作りだ。ある年齢までに、そのようなシステムを自分の中にきっちりこしらえておかないと、人生は焦点を欠いた、めりはりのないものになってしまう。”
個人的には村上春樹がこれまで走ってきたレースを彼の目線でたどるのが楽しいです。
ちなみに執筆中の海外生活について書いたエッセイである”遠い太鼓”では、たびに出て走ることについて書いてます。こっちもおすすめ。
走る奴なんて馬鹿だと思ってた
同じく作家が書いた走ることのエッセイなんですが、"走ることについて語るときに僕の語ること"とは対照的な一冊。そもそもスタートからして健康状態が割と最底辺です。そこから一発奮起で毎日走り続け(最初は数百メートル)、やがてフルマラソンを完走するまでのチャレンジや怪我への向き合い方が、我々一般市民ランナー目線で、 ”あ、そんな張り切らなくても、自分らしく楽しめればいいんだ” と思わせてくれます。
ランニングする前に読む本 最短で結果を出す科学的トレーニング
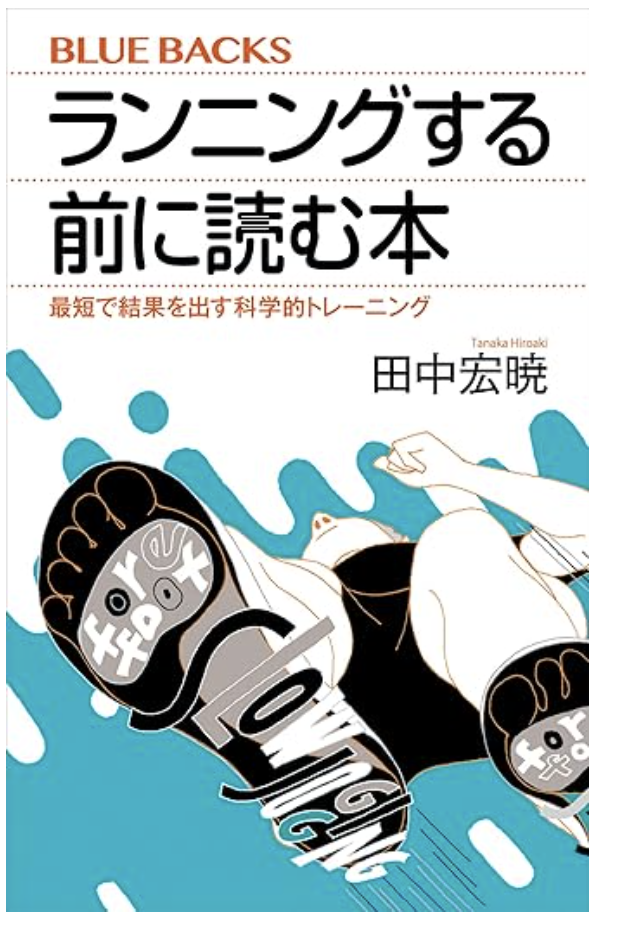
ランニングする前に読む本 最短で結果を出す科学的トレーニング
タイムに伸び悩んでいたときにたまたま手にとって、トレーニングに革命がおきた本。この本のやり方に沿って1年で15分以上(3:30 → 3:15)タイムが縮みました。
“ランニングする前に読む本”という表題のとおり、これから走ろうかなと考える人が知っておくべきランニングの始め方が書いてあり、大変参考になります。詳細を端折って書くと、ようはキツいトレーニングをせずとも、十分フルマラソンを走り切る走力もつくし、タイムは伸びるよ、という話です。
自分がこれは絶対人におすすめしたいという本を選んでみたんですが、こうして並べてみると、どれも生き方につながる内容だなーと思いました。
最後に、”EAT & RUN”からの一節を紹介してまとめます。
“食べることも走ることも、ごくありふれたシンプルな活動だ。(中略)気持ちを込めて気を配りながら行い、今このときをだいじにして謙虚になって行えば、こうしたシンプルな活動が超越への道につながる。
(中略)
人生はレースじゃない。ウルトラマラソンだってレースじゃない。そう見えるかもしれないけれど、そうじゃない。(中略)大事なのは、どうやってそのゴールに向かうかだ。決定的に重要なのは今の一歩、今あなたが踏み出した一歩だ。”


